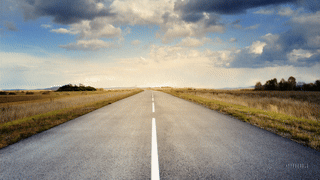『労務管理』のはじまりと「心理的安全性」
さまざまな偶然が重なり、学校を卒業して最初に就いた仕事が、『労務管理』の高度化を設立動機とする団体での業務でした。この選択は、後から振り返ると運命的なものであり、私のキャリア形成において重要な意味を持つものでした。
新入社員として配属された当初から、団体が主催する各種『労務管理』に関する研修やセミナーに運営スタッフとして携わる機会をいただきました。日々の業務を通じて、労務管理という分野がいかに幅広く、かつ深遠なものであるかを目の当たりにしてきました。最初は単純な裏方業務として、参加者の受付や資料の準備、会場設営などを担当していましたが、次第に企画段階から関わるようになり、研修プログラムの立案、募集案内の作成、講師との調整、さらには当日の進行までを一手に担うようになりました。このプロセスを通じて、労務管理の奥深さや重要性について徐々に理解を深めていきました。
労務管理について学ぶ中で、私が特に興味を持ったのは、その理論的な背景でした。教科書的には、1924年から1932年にかけて、ハーバード大学の心理学者エルトン・メイヨーによって行われた「ホーソン実験」が労務管理論の出発点とされています。この実験は、ウェスタン・エレクトリック社のホーソン工場で実施されたもので、従業員の生産性が職場の環境要因や金銭的インセンティブだけでなく、職場の人間関係や心理的要因にも大きく左右されることを明らかにしました。これは人間中心のアプローチを含む労務管理の基礎となったのです。
「ホーソン実験」で得られた最も大きな研究成果は、仕事の能率は職場の人間関係によって大きく左右されうる、ということを見出したことでした。この研究から、仕事の生産性を高めるため、従業員間の人間的な側面に焦点を当てたさまざまな研究が行われていきます。
最近では、エルトン・メイヨーと同じハーバード大学のエイミー・エドモンドソンが1999年に提唱した「心理的安全性」の考え方が注目を集めています。Google社がこの概念を基礎として社内実験を行い、「生産性が高いチームは心理的安全性が高い」ことを2015年に発表し、大きな話題となりました。
「心理的安全性」とは、個人が自分の意見を言うことや失敗を認めることによって批判や叱責を受けるのではないか、という不安を感じる事のない状態を持つことを指します。この概念は、企業の生産性だけでなく、審業員のやる気やイノベーションに大きな影響を与えることが明らかになりました。
今から約100年前に行われた「ホーソン実験」は、職場の人間関係における主要な結論を示しました。「同じ職場で働く従業員間の人間関係が良いほうが生産性が高い」という発見は、その後の人間関係の研究に大きな影響を与えました。そして、100年後の2015年、世界をリードするIT企業であるGoogleは、職場の人間関係が良好なチームほど生産性が高いことを再確認しました。この結論は、職場の人間関係の重要性を改めて意識させる機会となっています。
『労務管理』の共通性
100年間の歴史の中で、仕事の生産性を高めるための「労務管理」手法を見出すために、世界中の研究者が数多の実験を行い、数え切れないほど膨大な研究成果や新たな解釈を積み重ねてきました。
極端な例かもしれませんが、 1930年の「ホーソン実験」で明らかにされた 「人間関係」の良さがチームの生産性を高める、 という研究成果は、 2015年の「心理的安全性」が高いチームの生産性が高かった、 という実証実験の成果と一致しており、「職場を同じくする人とは仲が良い方が生産的な仕事ができる」というコアとなる主張は、時代を越えて共通しているように思えます。
その他にも、 1959年にフレデリック・ハーツバーグが「二要因理論」で主張した 「仕事の満足」は、 「達成すること」、 「承認されること」、 「責任」、 「昇進」、 「仕事そのもの」であり、 逆に「仕事の不満足」は 「給与」、 「会社の政策と管理方法」、 「監督(上司との関係)」である、 という考え方は、 60年以上経った今でもあてはなるものと思われます。
これらの研究成果は社会、産業経済などの変化にもかかわらず、人が働く場面において有用性を失わないものと考えられます。
実践すること、内省すること。
膨大な研究成果の中で、世界中の研究者や実務家からの批判に耐えながら今日まで受け継がれてきた『労務管理・労務管理論』には、地域や世代を超える普遍性が含まれている可能性があります。その背景には、時代や環境が変化してもなお、多くの企業や組織が共通して直面する課題を解決するための指針を「理論」が提供してきたという実績があるからかもしれません。
私がこの分野で大切にしていることの一つは、自らの価値判断に基づいて、普遍的と思われる理論を深く信じることです。しかし、それだけでは十分ではありません。企業や組織の実態に適応させるため、理論を実際に適用する際には常に内省を行い、状況に応じた最適化を続ける努力が求められます。労務管理の理論や方法論が一定の普遍性を有しているとはいえ、それらの知見を活かすには実際の職場における適切な運用が不可欠となるからです。
最近の研究や実践の中で注目されている「心理的安全性」を例に挙げてみましょう。心理的安全性とは、「チームの誰もが、批判や非難を恐れることなく、自分の考えや気持ちを率直に発言できる状態」と定義されています。この概念は、個人の自由な発言が許容される環境が、チーム全体の生産性や創造性の向上に寄与することを示しています。
実際、Google社が行ったプロジェクト・アリストテレスと呼ばれる実証研究では、心理的安全性が高いチームほど、生産性が高く、メンバー同士の協力がスムーズであるという結果が得られました。この結果自体は、理論としても直感的に理解しやすいものかもしれません。多くの人が、自分の意見を安心して表明できる環境のほうが、より良い仕事ができるという経験則を持っているでしょう。
しかし、こうした理論が広く認知されているにもかかわらず、実践の難しさが指摘されます。特に日本の企業文化においては、上下関係や暗黙の了解が強調される場面が多く、自由に意見を述べることが難しいケースが少なくありません。そのため、「心理的安全性」をチームに取り入れるには、単に理論を学ぶだけでなく、実際の現場での運用を見直す必要があります。
職場の人間関係が良い方が生産性が高まる、ということは、実に100年以上前から広く知られています。現在でも、職場の人間関係をテーマとした研修やセミナーは頻繁に開催されています。
しかし、職場で導入した『労務管理』施策が本来の目的を果たし続けるためには、施策そのものの運用状況や効果を継続的に見直し、改善する姿勢が必要となります。この「内省」のプロセスこそが、労務管理の成功を支える鍵だと考えられます。
その労務施策が本当に職場の風土に適しているのか。
当初の目的を達成できているのか。
改善すべき点があるのか。
職場全体に労務施策の重要性が浸透しているのか。
このような導入後の内省と改善を繰り返すプロセスこそが、理論で明らかにされた生産性を高める職場の状態を維持するための基盤となります。
「何を信じて、いかに内省を続けるか」
日々、新しい知見や研究成果が次々と生み出され、瞬く間に世界中に発信されています。私たちはこれまでにないほど多くの情報にアクセスできるようになりました。しかし、この情報過多の時代において、膨大なデータの中から「何を信じるべきか」を判断することは、非常に難しい課題となっています。
さらに、信じた考え方・理論を組織に浸透させるためには、継続的な「内省」の姿勢が求められます。内省とは、過去の行動を振り返るだけでなく、その行動の背景にある価値観や目的を再確認し、常に「今」に適合させ続ける改善のプロセスです。
「何を信じ、いかに内省を続けるか」。
この問いは私の基本的な指針であり、行動や判断の原点とも言えるものです。
【参考・引用元】
・『産業文明における人間問題』エルトン・メイヨ―(1967)
・『仕事と人間性―動機づけ‐衛生理論の新展開』フレデリック・ハーツバーグ(1968)